「気合いで乗り切るしかない」
──そんな言葉、現場で何度聞いたことか。
人手が足りない。納期は詰まっている。
結局、作業者の“根性”でまわしてしまう。
でも正直、それが続く現場は長くもたない。
なぜなら、人のがんばりだけで回る仕組みは、必ず限界がくるからだ。
疲労は溜まり、ミスが増え、離職が出る。
それでも「がんばりが足りない」と言われる。
オレも、そんな現場を何度も見てきた。
人出不足を理由に、休日を削って回す。
無理な計画を気合いでゴリ押しして、上にはドヤ顔で報告。
でも現場は、静かに壊れていった。
だからこそ言いたい。
人手不足の下で、絶対にやってはいけないのは「マンパワーに頼ること」だ。
本当に現場を守るのは、“がんばり”じゃない。
“仕組み”だ。
次に、なぜそう言い切れるのか──現場のリアルと心理の話をしていこう。
マンパワーに頼る現場の“あるある構造”

気合と根性でまわす現場
「気合いでなんとかしよう」
「とりあえず今日だけ乗り切ろう」
──そんなセリフ、どこの現場にもあると思う。
オレも見た。
人手が足りないのに、生産計画だけはそのまま。
結果、作業者の根性でどうにか回していた。
休みは削られ、残業は当たり前。
「しょうがないよな」と笑いながら、みんな疲れ切ってた。
短期的には、確かに回る。
でも、そのツケは確実にくる。
疲労が溜まってミスが増え、
離職者が出て、残ったメンバーにまたしわ寄せがいく。
悪循環だ。
「がんばる人」が評価される歪んだ構造
こういう現場では、決まって“がんばる人”が重宝される。
どんなに無理な仕事でも「ハイ」と返事して動く人。
逆に、「ムリです」と言う人は、評価を下げられる。
だから、みんな無理をする。
熱があっても出勤する。
手を抜かない真面目な人ほど、先に限界がくる。
その間、管理者はどうするか。
「よくやってる」「根性あるな」と褒める。
気づけば、“がんばる人が損をする現場”になっていた。
実際、厚労省や産業衛生学会のデータでも、
長時間労働や休みの削減は疲労・判断ミス・事故増加に直結するって出てる。
つまり、「努力で回す仕組み」は、
裏では“壊れる仕組み”になってるってことだ。
現場の声が消える瞬間
一番怖いのは、根性文化が“声”を消すこと。
「もう限界だ」「こうすれば楽になる」
──そんな意見が出なくなる。
現場の雑談や愚痴の中には、改善のタネが山ほどある。
でも、疲弊してる現場ではそれを拾う余裕がない。
「どうせ言っても変わらない」と思わせたら、
もう何も生まれない。
人が頑張るより先に、仕組みを頑張らせる。
それができないと、現場は静かに崩れていく。
セクションまとめ
気合いと根性でまわす現場は、短期では走れても、長期では壊れる。
「がんばる人」に頼る構造を放置したままでは、誰も救われない。
なぜ“人のがんばり”では続かないのか
「努力=正義」という思い込み
オレたちはずっと、「努力は裏切らない」って教えられてきた。
苦しくても頑張るのがえらい。
途中で弱音を吐いたら負け。
──そんな価値観、身にしみついてるよな。
でも、心理学の研究ではこう言われてる。
「人は、努力したこと自体に“意味”を感じる傾向がある」
(Inzlicht, M. Experimental Evidence That Exerting Effort Increases Meaning, 2023)
つまり、“がんばった”という行為そのものが報酬になってしまう。
だから、ムリな環境でも「頑張ったから意味がある」と思い込みやすい。
その結果、構造の問題を“根性でカバー”する文化ができる。
報われない努力が、心を削る
もう一つ有名なのが「努力−報酬不均衡モデル」だ。
「努力に対して報酬・休息・評価が見合わない状態は、
心身にストレスを生む」(Siegrist, 1996/日本でも確認あり)
ResearchGate: Effort-Reward Imbalance Model in Japanese Working Population
根性で頑張っても、給料も変わらず、休みも減り、
「ありがとう」も言われない。
そうなると、やる気どころか、心がすり減る。
国内調査(BMC Public Health, 2020)では、
職場ストレスが高い人は離職リスクが男性で3倍、女性で1.5倍高いと報告されてる。
出典:BMC Public Health
つまり、「がんばる人が辞める現場」ができあがってしまう。
「根性文化」はどこから来たのか?
この“気合で乗り切る”文化、根は深い。
オレらの世代は、スポコン漫画や部活で「最後まで諦めるな」「根性で勝て」って叩き込まれた。
実際、スポーツ心理の研究では、
「チーム一体感(team cohesion)がメンタルに影響する」と言われてる。
(例:PMC: Team Cohesion and Performance)
この“チーム一丸”の発想が、現場にも転写されてる。
みんなで乗り切るのは悪くない。
でも、“がんばりでしか回らない”は違う。
あれは、若い頃の部活なら美談になるけど、
仕事では、再現性のない運用になるだけなんだ。
心理の罠を抜けるには
大事なのは、「がんばる」ことを否定することじゃない。
**「がんばりを前提にしない仕組み」**を作ること。
努力は最後の一押しであって、土台じゃない。
その土台をつくるのが、仕組みであり、リーダーの役割だ。
根性文化のままでは、人も品質ももたない。
けど、仕組み化すれば、人手不足でも現場はまわせる。
実際、経産省の調査でも、仕組みや自動化を進めた企業ほど離職率が下がってる。
(出典:経産省「ものづくり白書」2018)
セクションまとめ
「がんばること」は大事。
でも、それを前提にしたら現場は壊れる。
仕組みで支え、努力を最後の“プラスα”にできたとき、
本当の“強い現場”になる。
人の声を仕組みに変える

アイデアは、現場の雑談に落ちている
もっとこうすればいいのに」
「これ、ムダじゃね?」
──そんな言葉、現場の休憩時間でよく出るよな。
オレは、そんな何気ない雑談の中から改善のヒントを得た。
それをもとに現場改善を実施したんだ。
最初は、変化を嫌う作業者たちから反発もあった。
「今のままでいいじゃん」「また余計なことを…」ってな。
でも、効果を数値で見せて、一人ひとりに丁寧に説明していった。
少しずつ理解を得て、気づけば現場全体が動き始めた。
結果、人手不足の中でも、
これまで頻発していたトラブルをほぼゼロに抑えることに成功。
そのおかげで、トラブル処置に使っていた時間や、
品質ロスがほとんどなくなった。
つまり――
マンパワーに頼らずに、余裕を持って生産できる現場が実現したんだ。
あのとき思った。
「仕組みが人を助ける」って、こういうことなんだって。
人出不足でも回るのは、“相談できる現場”
リーダーが「忙しいから黙って動け」って空気を出すと、
現場の声は一瞬で消える。
でも、テンパってる時ほど、作業者に相談した方がいい。
「どう思う?」「こうしたら楽になる?」
その一言で、現場の頭が一気に動き出す。
作業者は一番“現物”を触ってる。
だから、リーダーよりも早く改善のヒントを見つけてることが多い。
経営コンサルが何百万かけても出せない答えが、
現場の雑談の中にゴロゴロ転がってるんだ。
仕組みをつくるのは、特別なことじゃない
仕組みって言うと、大げさに聞こえるけど、
最初は「決めごとを共有する」だけでもいい。
- この作業はA手順でやる
- 連絡は5分以内で返す
- 誰が抜けても回るように、マニュアルを残す
これも立派な“仕組み化”だ。
厚労省の調査(ものづくり白書 2018)でも、
94%の製造業が人材不足を課題に感じていると出ている。
出典:経産省「ものづくり白書」2018
だからこそ、「人に頼る」のではなく、「仕組みに頼る」ことが、
今の時代のリーダーの役目なんだ。
セクションまとめ
「現場の声」は、聞くだけじゃ意味がない。
拾って、形にして、仕組みに変える。
それができた時、人出不足なんてもう怖くない。
「仕組みで回す」リーダーが現場を守る
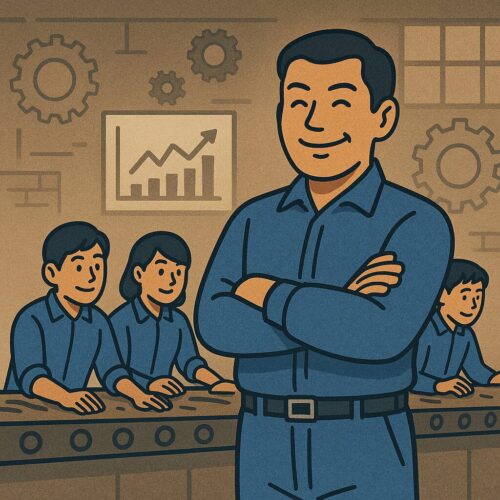
頼るのではなく、任せる
リーダーってさ、つい「自分がやらなきゃ」って背負いこむよな。
でも、“頼る”と“任せる”はまったく違う。
頼るってのは、相手の体力をアテにすること。
任せるってのは、仕組みの中で力を発揮できるようにすること。
人の気合いを当てにしたチームは、誰かが欠けた瞬間に止まる。
でも、仕組みで回しているチームは、誰が抜けても動き続ける。
それが本当の「強い現場」だ。
テンパったら、相談しよう
人手不足で現場がバタバタしてる時こそ、
「全部オレが何とかする」は一番危険。
むしろ、テンパった時こそ相談がリーダーシップだ。
作業者に、他部署に、時には上司に。
「これ、今のままだと回らないんです」って声を上げる勇気。
それは弱音じゃない。
**現場を守るための報連相(ほうれんそう)**だ。
未来工業のように「報連相禁止」にしても回ってる会社もあるが、
あれは仕組みと信頼が完成してるからこそ。
俺たちはまず、相談できる土台から作ろう。
「人を守る」は「頼りすぎない」こと
人を大事にするって、
「頑張らせないようにする」ことでもある。
休むことを悪とせず、
ラクする方法を探すことを“手抜き”と呼ばない。
その意識をチーム全体に浸透させることが、
リーダーのいちばん大事な仕事だ。
努力を否定するんじゃない。
努力を必要としない設計を作ること。
それが、仕組みで現場を守るってことなんだ。
セクションまとめ
「人手不足が怖いんじゃない。仕組みがないのが怖いんだ。」
気合いで走るのはもう限界。
仕組みで動く現場をつくることが、
人を守り、未来を守る一番の方法だ。
最後に一言
「気合いで乗り切る」って言葉、オレも何度も使ってきた。
でも今ならわかる。
あれは“限界を押しつける合図”だったんだ。
現場を守るってのは、人を守ること。
人を守るってのは、仕組みで支えること。
根性で回す時代は、もう終わり。
これからは、“仕組みで笑える現場”をつくろう。



