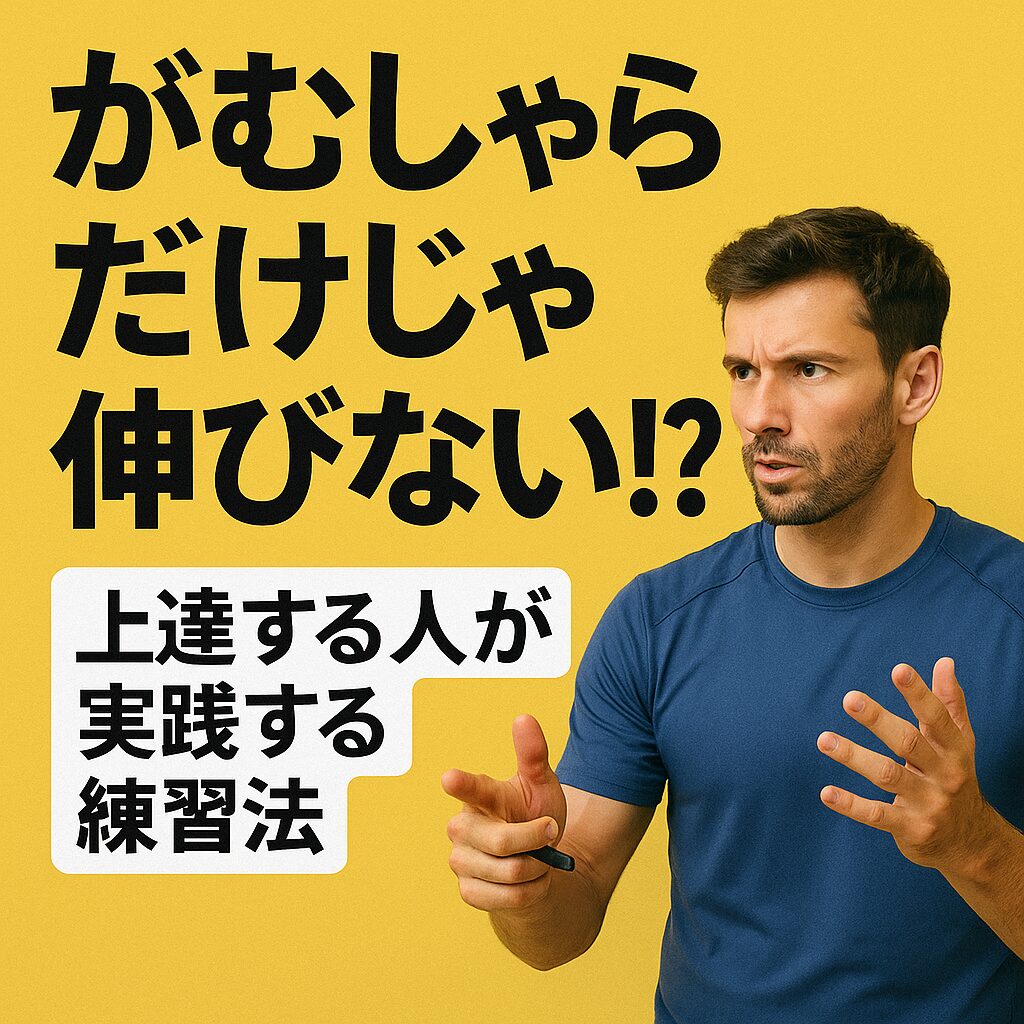頑張ってるのに、なぜか伸びない。
仕事も、スポーツも、趣味も、副業も──。
それ、もしかしたら「ただ数をこなしてるだけ」になってないか?
今日の申し送り:
上達したいなら、「感じる力」を育てろ。
量をこなせば、上達する?本当に?
仕事でも、スポーツでも、趣味でも、副業でも。
「とにかく数をこなせ!」って言われたこと、あるよな。
たしかに最初はそれで慣れることもある。
だけどな、ただ作業モードでダラダラ続けても、成長は止まるんだ。
俺も、中高で野球部のレギュラー、空手では地方大会入賞、サーフィンは全国大会出場、工場では最年少で課内最優秀社員。
でもどの現場でも、ただ量をこなすだけじゃ伸びなかった。
たとえば現場で、上司にこう言われたとする。
「とりあえず1日100件飛び込み営業してこい!」
でも、その100件を「ただ回っただけ」で終わったら、どうなる?
答えはカンタン。
次の日も、同じミスを100回繰り返すだけ。
スポーツでも同じ。
フォームが崩れたまま1000本素振りしても、悪い癖が体に染み込むだけだ。
つまり、
「数をやればうまくなる」ってのは、半分ウソ。
思考停止の練習は、成長を止める
人間の体も脳も、意識しないと変われない。
ただの反復作業は、変化を生まない。
たとえば、工場で同じ作業ばかり3年やらされたとする。
最初は必死だったのに、今はもう「手が勝手に動く」だけになってないか?
これ、裏を返すと、
「成長も止まった」ってことだ。
上達ってのは、
・今のやり方でいいのか?
・もっと良いやり方はないのか?
って、自分で疑問を持つところから始まる。
脳死でやってたら、その疑問すらわかない。
そりゃ、伸びないよな。
自分で感じて、自分で検証する

じゃあ、どうすればいいのか?
答えはシンプルだ。
「仮説検証」を自分でやること。
具体的には、
- 良い情報を集める
- 自分なりに噛み砕く
- 「これ試してみよう」と小さな仮説を立てる
- 実際に試してみる
- 良かった点・ダメだった点を振り返る
このサイクルを、何度も回していく。
たとえば、ゴルフでスイングを直したいなら、
「右肩をもっと落とせって言われたな。試しに意識してやってみるか」
↓
「あれ、球は飛んだけど曲がるな。じゃあ次は左足の踏ん張りを強めてみよう」
って感じで、自分で小さく試行錯誤していく。
この積み重ねが、
「自分の型」
を作っていく。
頭で考えず、体が自然に動くレベルへ
最初は、考えながらしかできない。
でも、正しい仮説検証を繰り返すうちに、だんだん体が勝手に動くようになってくる。
これがいわゆる
「無意識のうまさ」
だ。
たとえば、自転車に乗れるようになったとき。
最初は必死でバランスを取ろうとしたけど、今は自然にできるよな?
それと同じ。
上達のゴールは、
「意識しなくてもできる状態」
を作ることだ。
そしてそのためには、**「脱力」**も大事になってくる。
力を入れるのは簡単だ。
でも、必要なところ以外は力を抜く。
これができるようになると、体の使い方が一気に変わる。
【まとめ】
- 脳死で数をこなすだけでは、成長しない
- 上達には「仮説検証」のサイクルが不可欠
- 自分の感覚を信じて、小さく試していこう
- 最終ゴールは、無意識でも自然にできる状態
- 脱力を覚えたとき、さらに大きく伸びる
【次回予告】
ここまで読んで、
「よし、仮説検証って大事なんだな!」
って思ったかもしれない。
でも、こんな疑問も出てこないか?
「そもそも、何を仮説にすればいいんだ?」
「正しい情報って、どうやって選べばいいんだ?」
次回は、『上達のコツ【中編】|数をこなすだけじゃ超えられない壁──仮説検証が成長を変える』
そこを深掘りする。
**「上達する人の情報の拾い方、仮説の立て方」**について、具体例を交えて話していく。
続きも、楽しみにしててくれ。