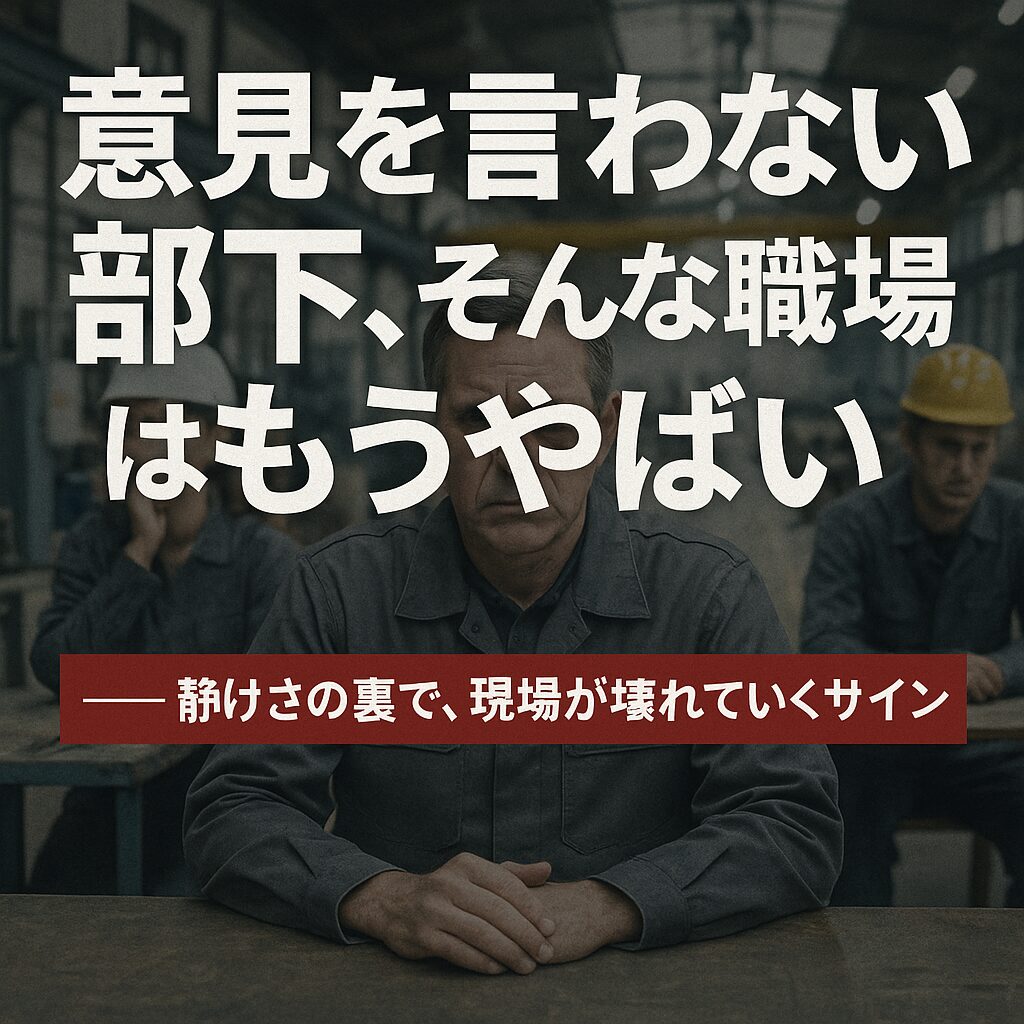現場で意見が出なくなったら、それはもう立派な末期症状。
正直、最近の現場、静かすぎないか?
誰も意見を言わない。
「何か気づいたことある?」って聞いても、シーン…。
一見、まとまってるように見えるけど、実はそれ、かなり危ない状態かもしれない。
なぜなら、意見を言わない職場は、すでに“壊れかけてる職場”だから。
作業者が意見を言わないのは
控え目な日本人だからか?
発言になれてないからか?
何も考えてないからか?
どれも的外れなリーダーの哀れな勘違い。
理由はもっとシンプルだ。
みんな「言ってもどうせ聞いてもらえない」と思っている。
あるいは、リーダーの高圧的な態度が“言えない空気”をつくっている。
その結果、現場では誰も何も言わず、表面だけが静かになる。
でもその裏では、不満がたまり、陰で愚痴が飛び交い、
最後は「もう限界だ」と静かに人が辞めていく。
沈黙は安心のサインじゃない。危険信号だ。
意見がでない職場ほど、実はヤバい

正直、「最近のうちは平和だよ」って言う現場ほど、ちょっと怖い。
誰もケンカしない。
誰も文句を言わない。
誰も意見を出さない。
一見まとまってるように見えるけど、実はそれ、危険信号だ。
なぜかって?
本当に元気な職場ってのは、ちょっとザワついてる。
「いや、それ違うと思います」とか「こうしたほうが早いっすよ」って声が飛ぶ。
そういう“ぶつかり”があるほうが、現場は生きてる。
でも今はどうだろう。
みんな黙ってる。
会議でも、班ミーティングでも、意見を求めても誰も口を開かない。
リーダーから見れば「静かでやりやすい」と感じるかもしれないけど、
その“静けさ”の裏では、不満や諦めがじわじわ溜まってる。
「どうせ言っても変わらんしな」
「言ったら面倒なことになるだけ」
──そんな声が、誰の心の中にもある。
つまり、「何も言わない」は「何もない」じゃない。
「何も言えない」状態になってるんだ。
その沈黙は、平和じゃなくて“麻痺”。
もう、現場の心が動かなくなってるサインなんだよ。
なぜ意見を言わなくなるのか
意見を言わない人って、ほんとは「何も考えてない」わけじゃない。
心の中ではちゃんと気づいてる。
「あれ、危ないんじゃない?」とか「こうすれば早いのに」って思ってる。
でも、言わない。
いや──言えなくなってる。
たとえば、前に一度「こうした方がいいと思います」って口にしたら、
リーダーに「そんなの無理だ」「余計なこと言うな」って言われた。
そんな経験が一回でもあると、人はもう次から言わなくなる。
「どうせまた否定される」
「めんどくさいと思われる」
そう思った瞬間、口は閉じる。
リーダーの態度ひとつで、現場の空気はガラッと変わる。
何気ないひとことが、誰かの“意見を封じるスイッチ”になることもあるんだ。
そして、日が経つにつれて「言ってもムダ文化」が根を張る。
みんな同じ顔で、同じ返事をする。
「はい」「わかりました」「特にありません」──それだけ。
でも心の中では、ちゃんと渋滞してる。
「またあの言い方かよ」
「俺の話、聞く気ないんだろうな」
「だったらもう、言わねぇよ」
こうやって、“沈黙の連鎖”が始まる。
最初は一人だったのが、次第にみんな黙るようになる。
すると、発言すること自体が浮くようになっていく。
結果、意見を出すより“空気を読む”ほうが安全になる。
そして、職場はどんどん“静かな現場”になっていく。
沈黙の裏で起きていること
静かな職場って、表面上は落ち着いてる。
でも、その静けさの下では、マグマみたいに不満が溜まってる。
誰も口に出さないだけで、休憩室では愚痴が飛び交う。
「またあのやり方かよ」「あの人、結局自分のことしか考えてないよな」
そんな声が、煙みたいに充満していく。
でも怖いのは、リーダーがその“煙”に気づかないことだ。
見た目は静か、トラブルも起きてない。
だから「うちはうまく回ってる」と思い込む。
けどある日、突然くる。
報告されなかったミスが、大きなトラブルにつながったり、
誰かが上層部や外部に不正をリークしたり。
気づいた時には、もう信頼関係がボロボロになってる。
そして、最後は“静かな退職”。
「辞める理由? まぁ…いろいろありますけど」
そう言って、何も語らずに去っていく。
辞める瞬間まで黙ってた人ほど、本当はずっと我慢してた。
でも、誰も聞こうとしなかった。
──沈黙の現場は、ゆっくり腐っていく。
音も立てずに、チームの力を奪っていく。
だから、「静かだからいい職場」とは限らない。
むしろ、誰も何も言わなくなったときこそ、
リーダーが一番敏感にならなきゃいけない瞬間なんだ。
意見は説得ではなく、理解から生まれる。
正直、昔のオレは“聞く”ことが下手だった。
部下と話してても、頭の中ではずっとこう考えてた。
「どうやって説得しよう。」
「どうやって言い負かしてやろう。」
「正論をぶちかましてやろう。」
──つまり、“どうやって言うことを聞かせようか”“どうやって自分の意見を押し通そうか”
そんなことばかり考えてたんだ。
だから、話を聞いてるようで実際は聞いてなかった。
相手の言葉が終わるのを待って、すぐ自分の主張をかぶせる。
いま思えば、あれじゃ誰も本音なんて言えない。
そんなオレの考えをガラッと変えたのが、
デール・カーネギーの本だった。
「他人に関心を持つことができれば、二ヶ月で友を得る。
自分に関心を持ってもらおうとすれば、二年かかる。」

この言葉を読んで、ハッとした。
オレはずっと“わかってもらおう”としてたけど、
“相手をわかろう”とはしてなかったんだ。
それから、意識して「聞く」をやってみた。
会議でも現場でも、まず「どう思う?」と聞く。
否定しそうになっても、グッとこらえて「なるほどな」と返す。
最初はぎこちなかった。
変に間が空いたり、気の利いた返しが出てこなかったり。
でも、それでも続けた。
すると少しずつ空気が変わっていった。
人がポツポツと意見を出すようになり、
「聞いてもらえる」空気が生まれた。
それまで“意見を言わない部下”だと思ってた人たちが、
実は“聞いてもらえなかった人たち”だったんだ。
この経験で痛感した。
リーダーの「聞く姿勢」が、職場の温度を決める。
スティーブン・R・コヴィー(『7つの習慣』)も言っている。
「多くの人は、理解しようとして聞くのではなく、答えるために聞いている。」
まさにオレのことだった。
“答えるために聞く”をやめて、“理解するために聞く”に変えた瞬間、
チームは少しずつ息を吹き返した。
そして最近、思うようになった。
「聞く」っていう姿勢ひとつでも、最初はぎこちない。
けど、それでいい。訓練すれば、信頼を得る聞き方のコツが自然と身につく。
そして、部下たちが本音を言い始めたら──
それは、あなたが“うまく聞けてる証拠”だ。
意見を育てるのは、リーダーの耳の使い方

オレが“聞く”を意識しはじめた頃、
毎日が試行錯誤だった。
「ちゃんと聞こう」と思っても、
つい口が出そうになる。
部下の意見に「いや、それは違う」と言いたくなる。
でも、グッとこらえて“聞く側”に回った。
そのうち、あることに気づいたんだ。
「聞く」って、リーダーの一番の仕事なんじゃないかって。
デール・カーネギーが言ってた言葉がある。
「他人に関心を持つことができれば、二ヶ月で友を得る。
自分に関心を持ってもらおうとすれば、二年かかる。」
この言葉を思い出して、
“部下に関心を持つ”ことを意識した。
プロジェクトの打ち合わせでも、
自分が話す時間を減らして、相手にしゃべらせる。
「なるほど」「それいいな」「もう少し聞かせて」──ただそれだけ。
すると、現場の空気が動き始めた。
意見が出る。
考えがつながる。
チーム全体が、“オレの指示”じゃなく“みんなの会話”で動き出した。
あのとき思った。
人は、話を聞いてくれる人のために動く。
でも、転職先の職場はその逆だった。
誰も何も言わない。
上が正しい。
間違っても訂正しない。
まさに“意見が死んでる職場”。
最初は静かでラクだったけど、だんだん怖くなった。
「この現場、何かあっても誰も気づかないな」って。
やっぱり“声のない現場”は末期症状なんだ。
気づけば、不満が限界まで溜まり、ある日突然、誰かが辞める。
そうやってチームは静かに崩れていく。
だから今、オレは思う。
「しゃべらせる場」を仕組みにすることが、リーダーの責任だ。
・朝礼で一人ずつ「気づいたこと」を言う時間をつくる
・会議では、リーダーが一番最後に話す
・1対1で5分だけでも雑談する
・意見を出した人を、まず褒める
こういう小さな積み重ねが、沈黙を溶かすんだ。
人は、「聞かれてる」と感じるだけで、安心する。
安心すれば、話し出す。
話せば、信頼が生まれる。
その信頼が、チームを動かすエネルギーになる。
つまり、「しゃべらせる場」は特別な仕組みじゃない。
リーダーが耳を開くこと、それ自体が仕組みになる。
静かな職場を変えたいなら、
まず“声を引き出す場”を意識的に作ること。
それが、沈黙の現場を再生させる最初の一歩だ。
意見が聞こえる職場が生きている職場。

静かな職場って、一見いい。
トラブルもないし、誰も怒鳴らない。
空気もピリピリしてない。
でも、その“静けさ”が長く続くときは、気をつけたほうがいい。
それは、安心じゃなく“諦め”かもしれない。
現場が本当に元気なときって、ちょっとザワついてる。
「それ違うと思います」とか「こうしたら早いっすよ」って声が飛ぶ。
笑い声や小さな口論がある。
そのざわめきこそ、現場が生きてる証拠だ。
オレも昔は、“静かな現場がいい現場”だと思ってた。
でも今は逆だ。
静けさは、危険信号。
人の声がある職場こそ、伸びるし、強い。
意見がぶつかる職場のほうが、ミスも早く見つかるし、
信頼も育つ。
そしてその空気をつくるのは、リーダーの“聞く姿勢”だ。
完璧に聞かなくてもいい。
うまく返せなくてもいい。
とにかく「聞こう」としてる姿を見せること。
それだけで、部下の心は少しずつ動く。
沈黙の現場を変えるのに、難しい理論はいらない。
必要なのは、「お前の話、ちゃんと聞かせてくれ」
その一言だけ。
静かすぎる現場ほど、リーダーの耳が試されている。
しんどいけど、ちょっと“聞いてみる”だけでいい。
その一歩が、現場をもう一度、**“声のある職場”**に変えていく。