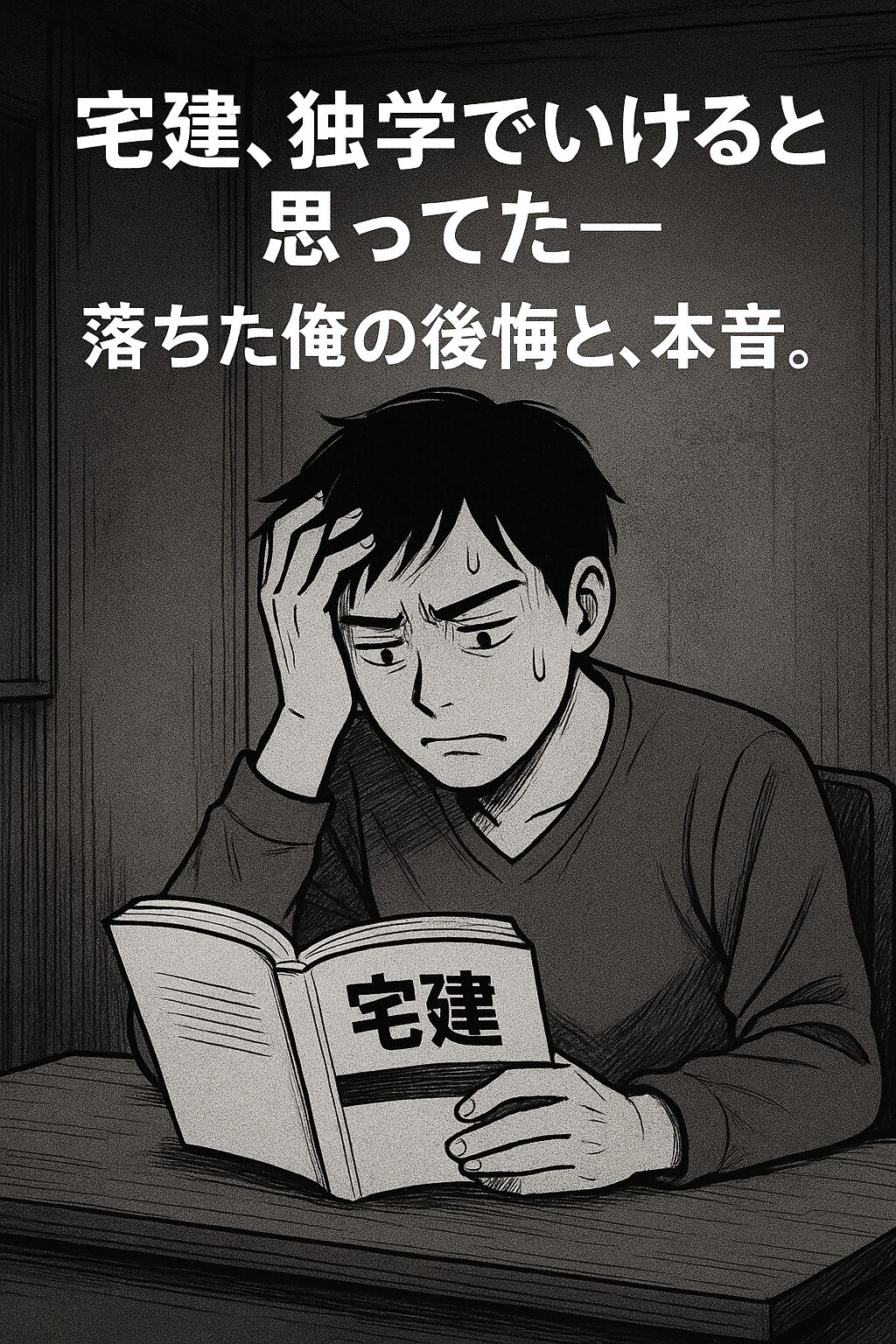宅建を独学で受けるって、意味あるのか?
結論から言うと、
“意味がある人”と“ムダになりやすい人”
がハッキリ分かれる。
そしてオレは――
2年連続で不合格になった「後者」だった。
努力した。
1回目(2023年)は
毎日2時間以上、週末は4〜5時間。
31点。
2回目(2024年)も
工夫して勉強法を変えたつもりだった。
34点。
でも結果は、
31点→34点。
あと1点足りずに、また不合格。
不合格は不合格。
そして、そのために削ってきた時間は、もう戻ってこない。
独学が悪いわけじゃない。
でも、「正しい方向に進めてるか?」を見誤ると、努力は平気で裏切ってくる。
この記事では、そんなオレの2年間の体験をもとに、
- なぜ独学がムダになりやすいのか
- どんな人なら独学でも戦えるのか
- 3年目で通信講座を選ぶ理由
を、本音で語っていく。
今、宅建を独学でやろうとしてるなら――
その選択、本当に“意味ある”かどうか、
一度立ち止まって考えてみてくれ。
独学で2年連続不合格の悪夢

「独学でもいけるっしょ」
2023年、最初に宅建を受けようと思ったとき、マジでそう思ってた。
努力には自信あるし、地頭も悪くない。
なんせ通信講座って高ぇし、もったいないじゃん。
このブログを読んでくれてる人は、私がいかにお金にシビアな人間かわかってくれてると思う。そんな私は極力お金を使いたくなかった。
でも結果、2年連続で落ちた。
2023年:ガチで頑張った初挑戦
スタートは2月。
平日は毎日1〜2時間、週末は4〜5時間。
テキスト読み込んで、過去問ガンガン回してた。
ぶっちゃけ、手応えもあった。
でも――本番は31点。
合格点は36点。
惜しいようで、全然届いてない。
2024年:やり方変えてリベンジ
今度は紙一枚勉強法(棚田不動産大学)も取り入れて、
「理解重視」「実践力」ってテーマで進めた。
「前より完成度高いし、これで受かるやろ」と思ってた。
実際の記録がこれだ。
毎日コツコツ、一問一問。紙一枚勉強法で、ここまでやった。

赤ペンで埋まっていく表が、オレの“やった証拠”だった。
でも、これだけやっても――
合格点には届かなかった。
――また落ちた。34点。
この年の合格点は38点。
年々、上がってる。難しくなってる。
通信講座は、最初から勧められてた
じつは最初に宅建受けようとしたとき、
お付き合いがある不動産会社の社長に「フォーサイトがおすすめですよ」って言われてた。
実績ある人だし、信用してた。
でも、「自分は独学でいける」って思っちゃった。
というか、お金がもったいなかった。
2回目のときも「お金より時間がもったいない」と思ったけど、
「いや、今回はいけるやろ」
「また金かけんのもな…」でやめた。
結果:
2年連続で、あと4点足りずに不合格。
いやもう、これが一番キツい。
一点足りないだけで、不合格は不合格。
そして、そのために削ってきた時間は二度と戻らない。
マジでシャレにならん。
というわけで、ここからようやく本題。
「独学って、なんでこんなムダになりやすいのか?」って話をしていく👇
「独学がムダになりやすい」
3つの理由

「独学でも受かる人はいる」
それは間違いない。
オレの周りにもいたよ。独学一発合格の人。
でも、その人らってだいたい
・高学歴
・他の資格も持ってる
・試験慣れしてる
こういうタイプ。
オレみたいに、社会人になってから勉強から離れてた人間が、
ノー武器で戦うにはキツすぎた。
実際、オレが独学でやってて「これはムダになってるかも…」って思ったポイントはこの3つ👇
範囲が広すぎて、全体が見えない
宅建って、ほんとに範囲が広い。
民法、宅建業法、法令上の制限、税・その他…
それぞれに細かいルール、用語、例外だらけ。
最初のうちは「全部ちゃんと覚えなきゃ!」ってなるんだけど、
独学だとどこが重要で、どこを捨てるかの判断がつかない。
結果、どうでもいいとこに時間使って、点につながらない。
特に宅建業法なんて点数配分デカいのに、民法ばっかり必死にやってたオレ…
今なら自分に言いたい。「そこじゃないぞ」って。
過去問だけ回して“できた気”に
独学あるあるだと思うんだけど、
過去問やって、間違えたら解説読んで「なるほどね〜」で終わるやつ。
で、次もまた解く。
正解する。
「おっ、覚えたやん」って思う。
…でもね、それ**“覚えてる”んじゃなくて、“見覚えがある”だけ。**
ちょっと言い回し変えられたり、選択肢の順番変えられると、もう迷子。
本番は“初見”をいかにさばけるか。
過去問周回だけじゃ、その感覚は身につかん。
継続がむずい。計画も崩れる。
これは社会人なら共感してもらえると思う。
- 仕事終わって、クタクタで勉強どころじゃない日
- 「今週こそ詰めよう」と思ってたのに、急な休日出勤
- 家族の用事、体調不良、飲み会…etc
予定通りになんて、ならんのよ。
オレもスケジュール組んでたけど、現実はボロボロ。
で、空いた日は「あれ?前どこまでやってたっけ…?」からの、やる気ゼロ。
積み上げたはずでは受からない。
この3つ、どれか1つでも当てはまったら、
「頑張ってるのに手応えがない」状態になる可能性が高い。
頑張ってるからこそ、キツい。
毎日時間は使ってるのに、成果に結びつかない感覚。
オレもそうだった。
だから言える。
独学はムダじゃない。でも、ムダになりやすい。
自分にとって“ムダにならない環境”を作れるかどうかが勝負。
独学が厳しくなってる
“もう一つの理由”
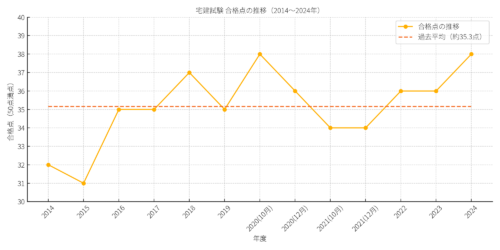
そして、もうひとつ声を大にして言いたいのが、
最近、宅建試験そのものが難化してきてるってこと。
実際、ここ数年の合格点を見てほしい。
- 2023年(令和5年):36点
- 2024年(令和6年):38点
→ 50点満点中だから、合格ラインが76%を超えるハイレベル。
これは完全に「基本だけじゃ足りない」って流れになってきてるってこと。
応用力、横断的な理解、そして“初見問題への対応力”が求められてる。
オレもまさにそれでやられた。
過去問は周回してた。暗記もした。
でも、本番で出てくる“ちょっと捻った問題”になると、
「あれ、これ見たことない…」
「…うわ、模試やっときゃよかった」
ってなる。で、あと1点足りない。
独学は、「自分で全部設計して、正しい方向に積み上げていける人」には意味がある。
でも、試験が年々難しくなってる今、昔より“独学のハードル”は確実に上がってる。
だから、なおさら問いたい。
次はその続き、
「じゃあ、独学でうまくいく人と、ムダになりやすい人って何が違うのか?」
って話をしていくよ!
独学が通用する人。しない人
「独学で一発合格しました!」
SNSとかでもよく見るけど――
そういう人って、だいたい“できる人”なんよ。
独学合格者は、だいたいこんな感じ
- 元々大学受験でガチ勉強してた
- 他の資格(簿記・行政書士・FPとか)も持ってる
- 勉強習慣がしっかりある
- 「情報の取捨選択」が自分でできるタイプ
つまり、試験慣れしてる人。
知識の覚え方とか、問題パターンの読み方とか、すでに頭に“型”がある。
そりゃ独学でも受かるよなって感じ。
勉強の素人は勉強を舐めている。
- 社会人になってから勉強はほぼしてない
- スケジュール管理も自己流
- 正直、どこから手をつけていいか不安だらけ
そんな人間が、いきなりフルマラソン走ろうとしてるようなもん。
しかも、地図なし、水なし、靴も合ってない。
そりゃ途中でバテるよね。
宅建の合格率は“狭き門”
● 宅建の合格率は 例年15〜17%前後。
(令和5年度:合格率17.2%/合格点38点)
受験者は約30万人。そのうち合格するのは5万人ちょい。
10人中8〜9人は落ちてるってこと。
しかも、ここ数年で合格点がじわじわ上がってる。
昔より、明らかに難化傾向。
通信講座を使った人の合格率
たとえば有名な通信講座「フォーサイト」の公式データを見ると、
受講者の合格率は平均より圧倒的に高い。
フォーサイト利用者の合格率(令和5年度):67.8%
全国平均合格率(同年):17.2%
※もちろん「講座使えば100%受かる」わけじゃないけど、
正しいやり方を教えてもらって、それを実行できる環境があるだけでこれだけ差が出る。
地頭より「環境の差」の方がデカい
オレも最初は「独学でいけるっしょ」って思ってた。
でも実際は、やり方が間違ってたら、いくら頑張っても届かない。
独学で合格する人=優秀
独学で落ちる人=凡人
…じゃなくて、
独学で受かる人=すでに“受かる環境”を自分で作れる人
独学で落ちる人=そこを間違えたまま、時間だけ使ってしまう人
この差はマジでデカい。
オレは2回落ちて、ようやく気づいたことがある。
それは――
宅建に合格するのは、“選ばれた一部の人”だってこと。
誰が受かってるのか?
“合格者のリアル”俺分析

合格率は毎年17%くらいって言われてるけど、
その中の17%がどんな人たちで構成されてるのか、意外と見えてない。
だから今回は、オレなりに**「誰が受かってるのか」**をランキングと数字で分解してみた。
完全に主観だけど、2年分の地獄を味わったリアルな体感ベースだ。
資格スクールや専門学校に通ってる人(約30〜35%)

- 毎日の勉強リズムを崩さず管理してもらえる
- 苦手や不安が出た時もすぐに相談できる
- 模試・復習・本番対策が“セット”で揃ってる
→正直、合格に一番近いポジション。
不動産業界の人(+5点免除あり)|約20〜25%

- 実務で出る法律や用語に日常的に触れてる
- 知識の定着が“仕事ベース”だから強い
- 5点免除で実質の合格ラインが下がるのもデカい
試験慣れしてる人(高学歴・資格持ち)|約15%

- 限られた時間で結果を出す“勉強筋”が鍛えられてる
- 情報整理、要点把握、スケジューリング…全部うまい
通信講座を活用してる人|約15%

- 自分で全部調べて選ばなくていい
- 時間と労力の“浪費”を避けやすい
- 特に最近はフォーサイトやアガルートなど、内容もかなり実戦向き
別業界×独学×2回目以上の挑戦者|約10%

- 前回の反省を活かして挑めるかどうかがカギ
- 工夫・戦略・環境の見直しができるかで、結果が分かれる
別業界×独学×初回受験(=昔のオレ)|約5%以下
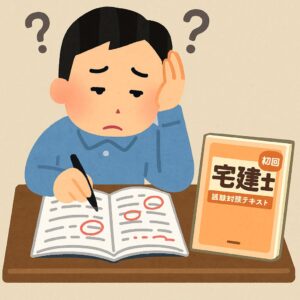
- そもそも試験の構造も配点感覚もわからない
- 暗記はしてるけど「問われ方」に慣れてない
- ひねられたら一発アウト、模試もやれてない、方向ミスも気づかない
6位スタートってどれくらい厳しいのか?
オレがざっくり計算してみたら、
このポジションから合格できる確率、約0.8〜1%。
合格者全体の17%の中でも、6位層が5%くらいしかいない。
つまり、100人受けて受かるのが1人くらいってこと。
結論:その位置から受かるの、マジで奇跡に近い
オレはその「6位スタート」で2回落ちた。
努力はした。でも方向も精度も、たぶん間違ってた。
だから今年は、戦い方を変える。
ようやく「合格者の側」に寄っていける方法を選んだ。
あなたは今、どのポジションにいる?
そしてその場所から――ほんとに受かると思えるか?
今年は“やり方”を変える。
フォーサイトを選ぶ理由

2025年、オレは3回目の挑戦をする。
でももう、同じやり方はしない。
今年は、最初から通信講座を使う。
フォーサイトを選んだ。
実は、最初から勧められてた
これは前にも書いたけど、
一番最初に宅建を受けようと思ったとき、不動産会社の社長が言ったんだよ。
「本気で取りたいなら、フォーサイト使っとけ」って。
宅建に合格してるどころか、現場でバリバリやってる人の言葉。
説得力しかなかった。
でも、聞かなかった。
当時のオレはこう思ってた
- 地頭あるし、独学でいけるでしょ
- 勉強は苦じゃない。努力できる
- 、通信講座って高いしもったいない
正直、「自分だけの力で取りたい」って意地もあった。
2回目の前も、「今度こそ通信やるか…」って思ってはいたけど、
結局また「いや、今回は独学でもいけそう」とか思ってスルー。
結果は、2年連続で不合格。
そして今、こう思ってる。
努力は足りてた。時間も使った。
でも“方向”が間違ってた。
合格に必要なのは、根性じゃなくて“ルート”だったんだ。
フォーサイトを選んだ理由
- もともと信頼してる人からのオススメだった
- 合格者の声もリアルで、講座の流れが具体的だった
- 値段はかかるけど、2年分の受験費用と時間の損失の方がよっぽど高い
しかも、
合格者の平均点が高くて、学習効率がいいってデータも出てる。
正直、「もっと早く使っときゃよかった」って後悔はある。
でも今はもう、合格まで最短距離で行くことしか考えてない。
その独学、本当に意味あるか?

最後にもう一回だけ言わせてほしい。
独学のメリットって、たしかに“お金がかからない”ってとこかもしれない。
でも、不合格だったときの「戻ってこない時間」は、それ以上に痛い。
そして、あと1点届かなかったときの絶望感。
あれはマジで、2回も味わうもんじゃない。
だから今年は、オレは変える。
やり方を、武器を、選びなおす。
「独学でいけるか?」じゃなく、
「このやり方で、ほんとに受かるのか?」って、
今の自分に問い直してみてくれ。
努力したい気持ちはわかる。
オレもそうだった。
「自分の力で取りたい」「無駄な出費は避けたい」――全部わかる。
でも、2回落ちて思った。
独学ってまじで意味ある?
あと1点届かなかったとき、
戻ってこない時間に気づいたとき、
もう「頑張ったからいいや」なんて気持ちにはなれなかった。
だから最後に伝えたいのは、これだけ。
今のあなたにとって、
「その独学、ほんとに意味あるか?」
一度立ち止まって考えてみてほしい。